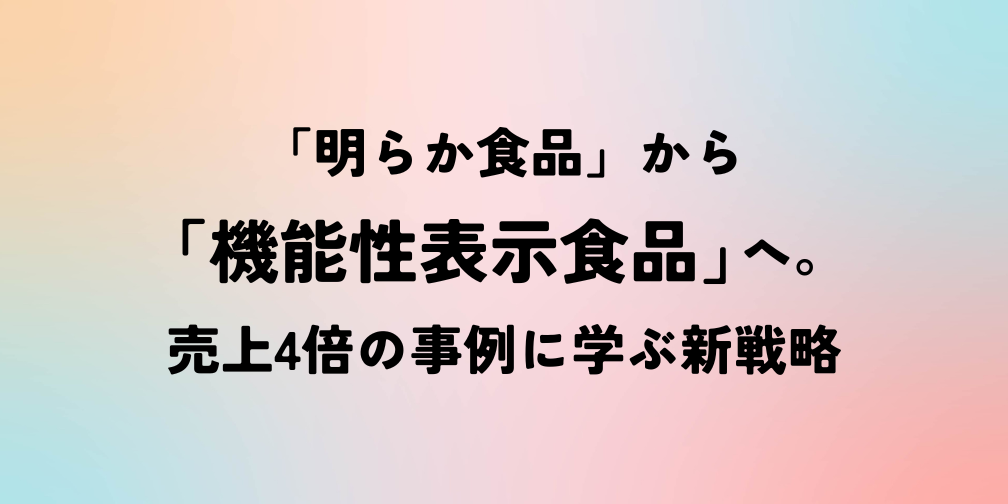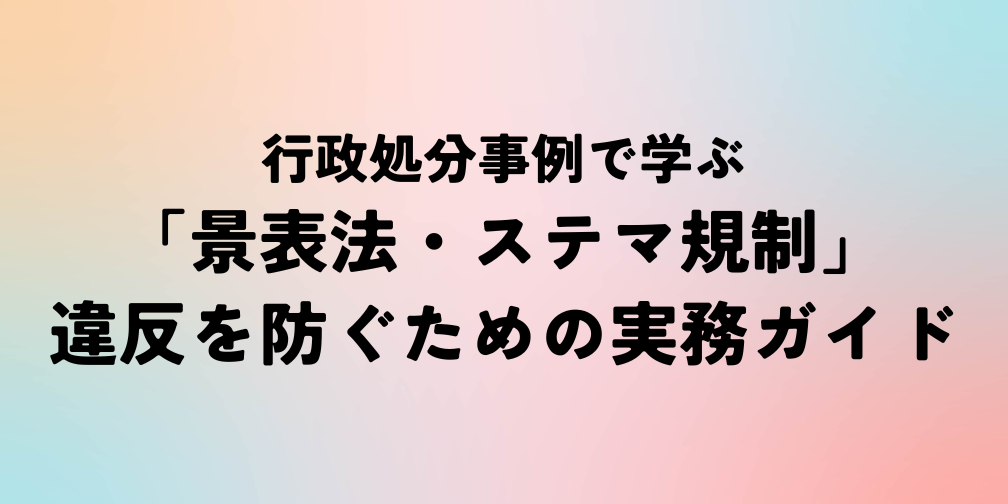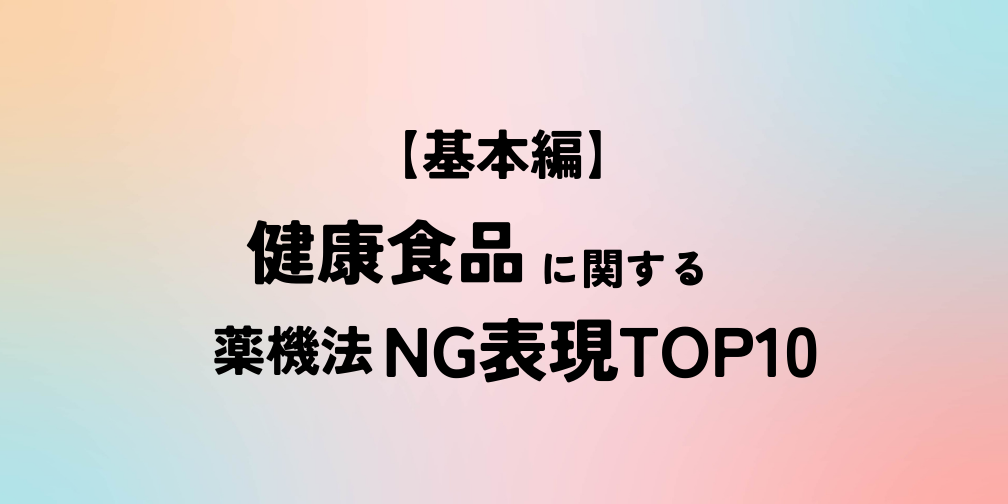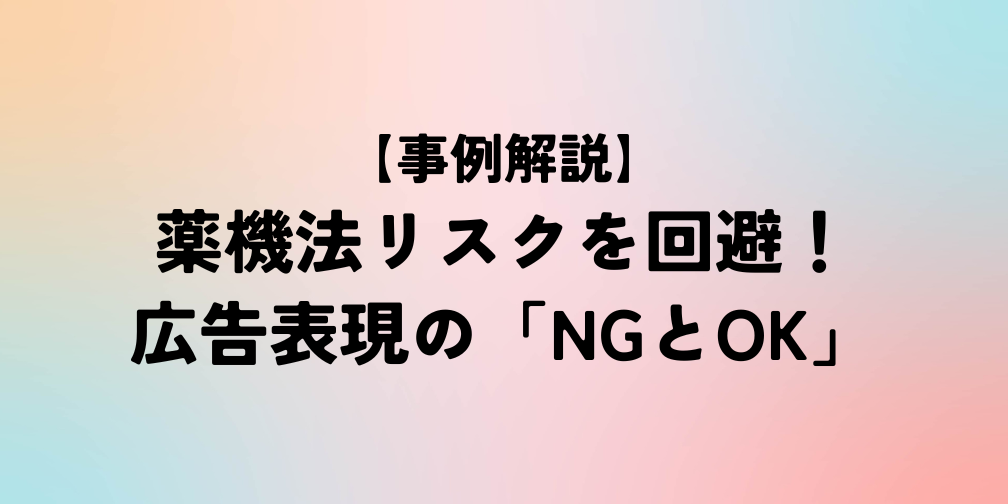2025/10/07
薬機法、医療広告ガイドライン、景表法。自社のビジネスに適用されるのは?
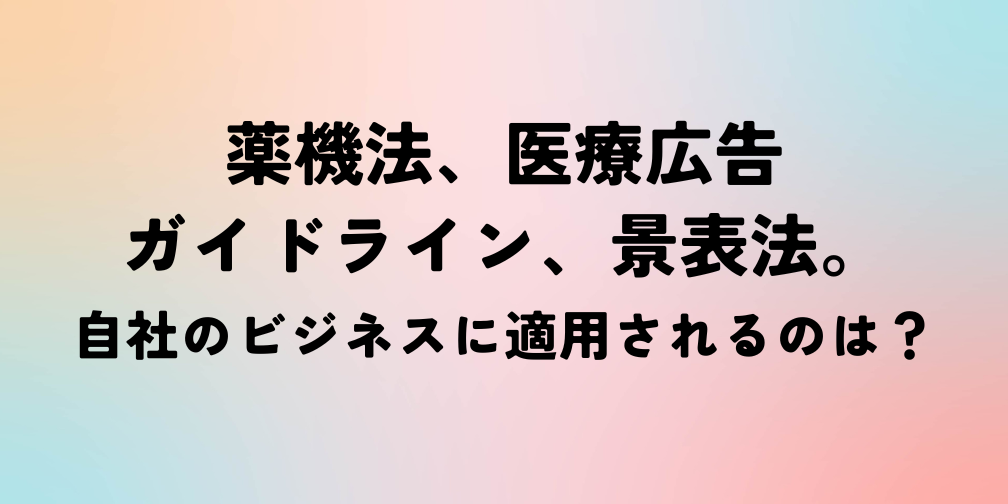
売上の拡大や消費者の獲得において、広告やプロモーションは不可欠な要素。
しかし、人の身体に関わる分野では、消費者を守るための厳格な法律やガイドラインが存在する。
その代表となるのが、「薬機法」「医療広告ガイドライン」だ。
また、身体への影響を直接謳わない商品やサービスにおいても、消費者を不当な表示から守るための「景品表示法」がある。
これらの法律やガイドラインは、それぞれ異なる目的を持ち、適用される業種や業態も多岐にわたる。
今回は、それぞれの法律・ガイドラインの概要と、どのような業種・業態が適用対象となるのかを詳しく解説していきたい。
薬機法
薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品といった製品の製造、販売、広告について規制する法律のこと。
正式には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という。
消費者の生命や健康に関わるこれらの製品が、品質、有効性、安全性を確保された上で適切に供給されることを目的としている。
適用される業種・業態の例
製薬会社・医療機器メーカー
医薬品、医療機器の製造販売を行う企業は、当然ながら薬機法の厳しい規制対象となる。
製品の承認・認証から製造管理、品質管理、そして広告に至るまで、広範囲にわたる規制が適用される。
化粧品メーカー・販売会社
化粧品の製造販売を行う企業も、薬機法の規制対象になる。
特に「効能効果」の範囲については厳しく定められており、承認された範囲を超える表現は認められていない。
「シミが消える」「シワがなくなる」といった表現も、原則として薬機法違反となるので注意が必要だ。
関連コラム:【基本編】化粧品に関する薬機法NG表現TOP10
医薬部外品メーカー・販売会社
薬用化粧品、育毛剤、入浴剤など、人体に一定の作用を持つと認められた医薬部外品も薬機法の規制対象となる。
化粧品と同様に、承認された効能効果の範囲内での広告表現が求められる。
健康食品・サプリメント販売会社
健康食品やサプリメント自体は薬機法の直接の規制対象ではないが、製品に「医薬品的な効能効果」を標榜すると、未承認医薬品として薬機法違反となる可能性がある。
「病気が治る」「〇〇が改善する」といった表現は、特に注意が必要だ。
また、取り扱う商品が「一般健康食品」か「機能性表示食品」かによって、広告表現の幅が大きく変わってくる点も押さえておきたい。
関連コラム:【基本編】健康食品に関する薬機法NG表現TOP10
医療機関・美容クリニック
内科や外科などの一般的なクリニック、そして美容クリニックともに、日々の診療で使用する医薬品や医療機器は、薬機法上の厳格な規制を受ける。
これらは製造から販売、使用、そして広告に至るまで、薬機法を遵守しなければならない。
特に、自由診療がメインとなる美容クリニックでは、その広告表現も患者の選択に大きな影響を与えるため、薬機法および医療広告ガイドライン双方の観点から細心の注意が必要だ。
エステサロン
サロンで使用・販売する化粧品や医薬部外品は、薬機法上の規制対象となる。
また、サロンで用いられる美顔器や脱毛器などは医療機器ではなく、美容機器・雑貨扱いとなるため、治療や身体機能への影響といった医療機器的な効能効果を謳うことはできない。
その他、サプリメントなどを販売する場合、医薬品的な効能効果を標榜すると、未承認医薬品として薬機法違反となる可能性がある。
インターネット通販事業者
上記の製品をオンラインで販売する場合も、薬機法の広告規制が適用される。
サイト上の商品説明や広告バナーなども規制対象となるので注意したい。
ウェブサイト制作会社・広告代理店
薬機法に関連するウェブサイトや広告制作を請け負う場合、ガイドラインの内容を理解し、クライアントに適切なアドバイスを提供することが求められる。
不適切かつ悪質性の高い広告表現は、制作側も責任が問われる可能性があることに留意したい。
薬機法は非常に専門性が高く、表現一つで違反となる可能性があるため、該当する業種・業態の事業主は、常に最新の情報を確認しておくことが重要だといえるだろう。
医療広告ガイドライン
医療広告ガイドラインとは、厚生労働省が定める「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」のこと。
医療に関する広告について、患者が適切な情報に基づき医療機関を選択できるよう、虚偽・誇大広告や誤解を招くような表現を制限することを目的としている。
適用される業種・業態の例
病院・診療所
医療法に規定されるすべての病院および診療所(内科、外科、小児科、皮膚科、産婦人科など)が対象となる。
ウェブサイト、パンフレット、看板、テレビCM、新聞広告など、あらゆる媒体での広告が本ガイドラインの規制を受けることに留意したい。
なお、助産所も医療法上の広告規制の対象となる。
歯科診療所
歯科診療所も、医療法に規定される医療機関として、医療広告ガイドラインの規制対象となる。
一般的な診療内容に加え、審美歯科や矯正歯科など自由診療に関する広告においても、その表現はガイドラインに厳しく準拠する必要がある。
美容クリニック・美容外科
自由診療が中心となる美容医療も、医療行為である以上、医療広告ガイドラインの規制対象となる。
特に、施術前後の写真や、効果を保証するような表現、特定の治療法を過度に推奨する表現などには注意が必要だ。
美自由診療を行うクリニック
美自由診療を行うクリニック
保険診療だけでなく、AGA治療、ED治療、再生医療などの自由診療を提供するクリニックも、医療機関である以上、広告はガイドラインに従う必要がある。
ウェブサイト制作会社・広告代理店
医療機関のウェブサイトや広告制作を請け負う場合、ガイドラインの内容を理解し、クライアントに適切なアドバイスを提供することが求められる。
不適切な広告表現は、医療機関だけでなく、制作側にも責任が問われる可能性がある点に留意しておきたい。
医療広告ガイドラインでは、客観的な事実に基づかない体験談や、治療効果を保証するような表現、他の医療機関と比較して優れていると誤解させる表現などが禁止されている。
医療機関のウェブサイトについては、広告可能事項の限定解除の要件を満たすことで、医療法で定められた広告可能事項以外の内容も掲載可能となる。
詳しくは、厚生労働省から公開されている以下の資料で確認できる。
参考:医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書 (第4版)
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
景品表示法とは、商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示する「不当表示」や、過大な景品を提供する「不当景品」を規制する法律のこと。
正式には、「不当景品類及び不当表示防止法」という。
消費者が安心して商品やサービスを選べる環境を守ることを目的としている。
適用される業種・業態の例
景品表示法は、消費者向けに商品やサービスを提供するすべての事業者が対象となる。
特定の業種に限定されるものではなく、幅広いビジネスに適用されるのが特徴だ。
以下に、その一例を紹介したい。
一般小売店・飲食店
商品の価格、原産地、割引内容、メニューの構成といった表示全般が規制対象となる。
「限定〇〇食!」や「本日限り!」といった表現も、実際にその通りでなければ不当表示となる可能性があるので注意したい。
アパレル・雑貨店
素材、製造国、セール価格など、表示されるあらゆる情報に景品表示法が関わってくる。
「カシミヤ100%」と表示しながら実際は異なる場合や、不当な二重価格表示などは違反となる。
健康食品・サプリメント販売会社
薬機法だけでなく景品表示法も密接に関わってくる分野。
「痩せるサプリ」などの広告で、根拠のない効果を謳うと、優良誤認表示(品質に関する不当表示)として景品表示法違反となる。
今年に入ってからも、不当表示として1,000万円以上の課徴金を科せられた業者が出ている。
株式会社ハハハラボに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
化粧品メーカー・販売会社
薬機法の効能効果の範囲内であっても、その効果を裏付ける合理的根拠がなければ、優良誤認表示となる可能性がある。
例えば、「保湿力No.1!」と謳うなら、その根拠を示すデータが必要となる。
インターネット通販事業者
ECサイト上の商品説明、広告バナー、レビュー表示なども景品表示法の対象となる。
例えば、ユーザーレビューを偽造したり、良いレビューだけを恣意的に掲載したりすると、景品表示法違反となるので注意が必要だ。
また、消費者に広告であることを隠す「ステルスマーケティング(ステマ)」も、2023年10月1日より景品表示法違反の対象となっている。
ウェブサイト制作会社・広告代理店
消費者向けのウェブサイトや広告制作を請け負う場合、単に技術的な制作を行うだけでなく、表示されるコンテンツの適法性についても常に意識し、クライアントに適切なアドバイスを提供することが求められる。
不動産業者
物件の間取り、立地、設備、価格、周辺環境などの表示全般が規制対象となる。
おとり広告として実際には取引できない物件を掲載したり、都合の良い情報だけを強調して表示したりする場合も、景品表示法違反となる可能性が高い。
旅行会社
ツアーの内容、宿泊施設のグレード、食事の内容、料金など、さまざまな情報が規制対象となる。
写真と実物が著しく異なる場合や、追加料金が発生するにも関わらずその表示が不明瞭な場合などは注意が必要だ。
学習塾・予備校
合格実績や教材の内容、料金体系など、消費者に提示するあらゆる情報に景品表示法が関わってくる。
「合格率100%!」などと謳う場合は、その根拠を示すデータが必要となる。
金融機関
金融商品の金利、手数料、リスクなどに関する表示などが、代表的な規制対象として挙げられる。
消費者の誤解を招くような表現や、重要な情報を意図的に隠すような表示は不当表示となる。
各種サービス業(美容院、マッサージ、リフォームなど)
サービスの価格、内容、施術効果などが規制対象となる。
景品表示法においては、特に「優良誤認表示」(品質や内容が実際よりも優れていると誤解させる表示)と「有利誤認表示」(価格や取引条件が実際よりも有利であると誤解させる表示)が厳しく規制される。
広告表現には客観的な根拠が求められるため、事業者は表示の裏付けとなるデータを準備し、消費者に誤解を与えないよう細心の注意を払う必要があります。
まとめ
薬機法、医療広告ガイドライン、景品表示法。
それぞれ規制の対象や目的は異なるが、「消費者の保護」という共通の理念に基づいて制定されている。
自社のビジネスがどの法律・ガイドラインの適用を受けるのか、そしてどのような点に注意すべきなのかを正しく理解することは、コンプライアンスの遵守だけでなく、企業の信頼性を高める上でも必要不可欠といえるだろう。
これらの法律・ガイドラインを遵守することで、健全なビジネスの成長へとつながるだろう。